自分が購読している雑誌を読んでると、その本に『アウェー感』という言葉が出てきました。
それで、この言葉に興味が出てきて、色々調べました。
アウェー感とは?
「アウェー感」(Away-kan)は、主にスポーツや競技イベントなどのコンテキストで使われる表現で、試合やイベントが自分の本拠地ではない場所で行われるときの独特の雰囲気や感覚を指します。これは、応援するチームや選手が敵地で試合を行うときに感じる緊張感、興奮、または不利な状況への違和感などを表現する言葉です。
例えば、あるサッカーチームのファンが自分たちのホームスタジアムで試合を観戦するのと、他のスタジアムで試合を観戦するのでは、雰囲気や応援の仕方が異なり、その違いが「アウェー感」と呼ばれることがあります。アウェー感は、試合の結果や状況によっても影響されることがあります。
人間関係のアウェー感とは?
人間関係の文脈で「アウェー感」という表現は、通常、特定の場所や状況において、自分が他者との関係を築く際に感じる違和感や緊張感を指すことがあります。これは、自分が馴染みのない場所や新しい環境で他の人々と関わるときに生じる感覚を表現しています。
たとえば、新しい職場や学校に入ると、周囲の人々との人間関係を築く際に最初は違和感を感じることがあります。これは、「アウェー感」の一例と言えます。自分が馴染みのある環境ではなく、新しいコミュニティやグループに加わることによる状態です。この感覚は時間とともに軽減され、適応していくことが一般的です。
『孤立』とは違うんですか?
「孤立」と「アウェー感」は関連していますが、異なる概念です。
「孤立」は一般的に、他の人々とのつながりが乏しい状態を指します。孤立している人は、社会的な接触が少なく、孤独感を抱えている可能性があります。これは主に個人が他者とのコミュニケーションを欠いている状態を指す言葉です。
一方で、「アウェー感」は、特定の状況や場所での違和感や緊張感を指し、主に新しい環境やコンテキストにおいて他者との関係を築く際に感じるものです。アウェー感は一時的なものであり、新しい状況に慣れるにつれて軽減されることが期待されます。
要するに、「孤立」は社会的な孤立を指し、人々とのつながりが乏しい状態を表す一方で、「アウェー感」は特定の状況や場所での違和感や緊張感を指し、社会的なつながりの形成に焦点を当てたものです。
人が、何か新しい場所に来た初日にアウェー感を感じることがあります。
新しい場所に来た初日にアウェー感を感じることは一般的です。これは、未知の環境や新しい社会的なコンテキストに適応する際の一時的な心理的な状態を指します。いくつかの理由からこの感覚が生じます:
1.不慣れな環境:
新しい場所や環境には慣れていないため、周りの景色や慣習が不慣れに感じられます。
2.未知の人々:
新しい場所では通常、未知の人々と出会います。これらの人々との関係を築く際には、初めての出会いや社交があり、それが緊張感を生むことがあります。
3.新しい社会的ルール:
各環境にはそれぞれの社会的なルールや慣習が存在します。これに適応するため、最初の日は違和感を感じることがあります。
このアウェー感は通常、時間とともに軽減され、新しい環境に慣れていくことで解消されることがあります。積極的に新しい経験に取り組むことや他者とのコミュニケーションを通じて、適応が進むことが期待されます。
アウェー感の対語は何ですか?『ホーム感』ですか?
「アウェー感」の対語として「ホーム感」が考えられます。一般的に、スポーツや競技のコンテキストで使われる際、「アウェー」は自分の本拠地ではない場所を指し、「ホーム」は自分の本拠地を指します。そのため、自分が慣れ親しんでいる場所や環境で感じる心地よさや適応感を「ホーム感」と表現することがあります。
例えば、ある人が自分の故郷に戻ったときや、親しい友人や家族と共にいるときには、「ホーム感」を感じることができます。これは、慣れ親しんだ場所や人々に囲まれることで生じる安心感や心地よさを指します。
『アウェー感』も時間や月日が経つと『ホーム感』に変わるんですか?
はい、一般的にはそういった傾向があります。初めての場所や新しい環境において感じる「アウェー感」は、時間とともに慣れや適応が進むことで、「ホーム感」に変わることがあります。人は新しい状況に適応し、環境に慣れることで、最初は感じた違和感や不安が軽減され、心地よさや安心感が増していく傾向があります。
この過程は個人によって異なりますが、一般的には新しい環境での経験や人間関係の構築を通じて、初めての不安や違和感が減少し、自分の居場所を見つけることができます。新しい場所での経験や交流が積み重なることで、その環境が「ホーム感」を持つ場所となることがあります。
『アウェー感』
数年前、B型事業所『ライフデザインマーケティング』に就職した際、最初の日々には「アウェー感」をあまり感じませんでした。当時は人数も少なく、少人数ならではのアットホームな雰囲気が漂っていました。その後、時は過ぎ、事業所は拡大。利用者も増加し、今では大所帯の仲間たちが増えたことで、初めて感じる雰囲気が変わりつつあります。
最初に働き始めた頃は、少数の仲間との環境が比較的なじみやすく、自分のペースで業務に取り組むことができました。しかしこの頃、利用者が増加し、事業所が大所帯になると、新たに参加した仲間たちがアウェー感を感じることが予想されます。そんな中、自身が初めて経験したことを振り返りながら、同僚たちとの協力や理解が新しいメンバーたちにとって重要なものであることを再認識しています。
新たに参加した仲間たちは、初めての数日や数週間、未知の場所や新しい仲間たちに対して違和感や緊張感を抱くことがあるでしょう。それは、仕事だけでなく、人間関係の構築や環境への適応が必要なためです。自分も最初は同じように感じていました。しかし、その過程が一時的であることを知っていたからこそ、前向きな気持ちで新しい環境に飛び込んでいけたのでしょう。
今では、自分が慣れ親しんだ環境で働いている一方で、新たに参加した仲間たちがアウェー感を感じていることを理解しています。彼らが新しい環境に慣れ、居心地の良い「ホーム感」を感じられるよう、協力し合い、コミュニケーションを大切にすることが求められます。助け合いや理解があれば、アウェー感は時間とともにホーム感に変わっていくものです。それは、初めてこの事業所に足を踏み入れた私にとっても、今新たな仲間たちが感じていることに寄り添うことができる喜びであり、貴重な経験です。
新しい環境に飛び込む勇気を持つことは、成長や新たな発見の始まりでもあります。アウェー感を感じることは、新しい可能性に向けての第一歩であり、それが時間とともにホーム感へと変わっていく過程を楽しむことができます。同じ空間で働く仲間たちとともに、それぞれが持つアウェー感やホーム感を分かち合い、共に成長していくことこそが、豊かな経験となるのでしょう。

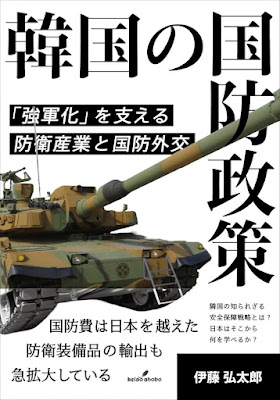


0 件のコメント:
コメントを投稿